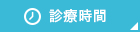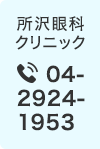屈折異常とは
人がものを見る仕組みはよくカメラに例えられます。例えば眼球の一番手前にある角膜と水晶体はレンズ、一番奥にある網膜はフィルムにあたります。そして、外から入ってきた光はレンズ役の角膜と水晶体を通り抜ける際に屈折を起こし、ピントが調節された状態でフィルム役の網膜へと映し出されます。
その際、ピントがちょうど網膜に合うように調節されると、見ているものは鮮明な像として映し出されます。しかし、何らかの原因で調節機能が正常に働かず、ピントが網膜よりも手前や後ろにずれてしまうと、見ているものはぼやけた像として映し出されます。この状態が屈折異常です。
屈折異常は大きく以下の3種類に分けられます。

近視
ピントが網膜よりも手前にずれて調節されるせいで、近くのものはよく見えて、遠くのものはよく見えない状態です。
遠視
ピントが網膜よりも後ろにずれて調節されるせいで、遠くのものはよく見えて、近くのものはよく見えない状態です。
乱視
ピントが一点に定まらず、複数に分散されるせいで、ものがいくつかに重複して見える状態です。
老視(老眼)
老眼とも呼ばれ、加齢と共に水晶体の弾性が失われて調整する力が弱まって、近くの物を見るときに焦点が合わなくなってきます。
屈折異常の検査
近視、遠視、乱視などの屈折異常を診断するにあたっては、主に以下のような検査を行います。また同時に、視力や屈折力に影響を与えるような目の病気の有無も確認します。
屈折検査
角膜や水晶体の屈折力を測ります。屈折力が強ければ近視、弱ければ遠視の可能性があります。
眼軸長(がんじくちょう)検査
眼軸長(角膜から網膜までの距離)を測ります。眼軸長が長ければ近視、短ければ遠視の可能性があります。
視力検査
屈折検査や眼軸長検査の結果をもとに、裸眼およびメガネなどで矯正した状態での視力をそれぞれ測ります。
屈折異常の対応方法
屈折異常は多かれ少なかれほとんどの方に見られるものですが、お仕事や家事、学業といった日常生活を送るにあたって不自由を感じるほどの屈折異常には、メガネやコンタクトレンズを用いて矯正することで通常は対応可能です。
ただし、まだ意思表示の難しい小さなお子さんの場合、屈折異常の発見の遅れが弱視のリスクを高めるので、日常的に保護者の方が気をつけてあげたり、一定の年齢になったら視力検査を受けて異常の有無を確認するなど、特別な対応が必要になる場合があります。
パソコンやスマートフォンといった目を酷使する情報端末の普及著しい昨今、大人になってから近視になる方が増えているといわれていますが、基本的に目にとってベストなのは矯正を必要としない状態です。日頃より目に負担のかからない生活を心がけ、現在の視力をキープし続けるよう努めることもまた大切です。
弱視とは
乳幼児期の屈折異常や斜視、あるいは他の目の病気などが原因で視力の発達が遅れてしまい、メガネなどで矯正しても十分な視力を得ることができなくなった状態を弱視といいます。
子どもの弱視治療に適切とされる時期を逸してしまった場合、大人になってからも視力の矯正が叶わず、運転免許を取得できなかったり、希望する職業に就けないなどの不都合が生じる可能性があります。そのため、お子さんがものを見る時の様子に気がかりな点がある場合には、保護者の方が早めに眼科を受診させてあげることが重要です。
子どもの視力発達と弱視
人間は生まれてすぐの赤ちゃんの頃から目がはっきりと見えているわけではありません。成長とともにピントの合った鮮明な像を見る経験を幾度も積み重ねることによって、視神経や脳の働きが刺激を受けて活性化していくことで視力も発達していきます。そして1歳半頃をピークに、最終的には8歳頃に発達を完遂するとされています。この視力が最も発達しやすい8歳頃までの期間を臨界期といいます。
この臨界期に屈折異常や斜視、あるいは他の目の病気などが原因で視力を発達させる機会を十分に与えられなかった子どもの場合、視力の発達が遅れたり止まってしまうことがあります。こうしたことが主な原因となって弱視が起きています。
子どもの屈折異常は早期発見を
まだ意思の表示が難しい小さな子どもの場合、自分の目がはっきり見えない状態であることをまわりにうまく伝えることができません。そのため、日常生活の中でお子さんがものを見る時の様子に何か気になる点がないか、保護者の方が気をつけてあげる必要があります。
目に何らかの異常がある小さな子どもには、主に以下のような特徴的行動が見られる場合があります。
- ものを見る時に目を細める
- ものを見る時に頭をかしげる
- ものを横目で見ようとする
- テレビを前の方で見る
- 目の前のものを持ち損ねることがある
こうしたそぶりに気づいた際や自治体の乳幼児健診などで視力に関する指摘を受けた際には、保護者の方が早めに眼科を受診させてあげることが重要です。
また、特別なそぶりがなくても、視力検査が可能になるといわれる3歳を過ぎたら一度眼科を受診して、異常の有無を確認しておくこともまた、お子さんの弱視予防につながります。
弱視の治療方法
屈折異常を原因とする弱視の場合、視力を矯正するメガネを常に着用して、ピントの合った鮮明な像を見る経験を積み重ねることで視力の発達を促します。
また、弱視が片目だけの場合、正常な方の目をアイパッチなどで塞ぎ、弱視の方の目だけで見る訓練を行うことで、視力の発達を促すこともあります。
視力が発達しやすいとされる8歳頃までの臨界期は、同時に弱視に対する治療の効果が最も上がりやすい時期でもあります。逆に臨界期を過ぎて以降の治療では効果が上がりにくくなることがわかっています。したがって、お子さんの目に異常があれば、まだ小さいうちにできるだけ早く発見してあげることが弱視の治療においては重要になります。
斜視とは
左右の目がそれぞれに異なる方向を向いている状態を斜視といいます。
左右の視線が向く先が異なるため、見ようとして目を向けているものに対する立体感や距離感の把握が難しくなったり、ものが重複して見えるなどの支障が生じます。
また、小さな子どもの斜視においてはいつの間にか片方の目しか使わなくなることが多く、弱視のリスクが高まる場合があります。そのため、お子さんの斜視に気がついたら、保護者の方が早めに眼科を受診させてあげることが重要です。
斜視の種類
斜視は片方の目が向いている方向によって、大きく以下の3種類に分けられます。
内斜視
片方の目が内側を向いている斜視です。特に乳幼児に多く発生します。そのほとんどは屈折異常の遠視によるもので、近くのものをよく見るために寄り目の状態になることが原因になります。
外斜視
片方の目だけが外側を向いている斜視です。年齢に関係なく発生します。病気や怪我などのせいで片方の目の視力が低下して、両眼視が難しくなると斜視が生じる場合があり、その多くは外側を向きます。
両眼視とは両目で見たものを脳で一つの像として認識することをいい、人は両眼視によって見ているものの立体感や距離感を把握しています。
上斜視・下斜視
片方の目だけが上または下を向いている斜視です。眼球を上下に動かす外眼筋に発生した異常が代表的な原因です。
斜視の治療方法
斜視を治療する目的は斜視の目を正常な向きに戻すことばかりではなく、斜視の目の弱視化を予防または改善し、ひいては両目の視力を改善して両眼視を実現することにあります。
なお、治療方法は斜視の種類や年齢などによって異なります
メガネによる治療
特に乳幼児に多く見られる遠視が原因の斜視の場合、視力を矯正するメガネを常に着用することで、目が正常な向きに戻ることがあります。
プリズムメガネによる治療
光の屈折作用を持つプリズムレンズを用いた特殊なメガネを着用することで、目に入ってくる光を斜視の目の向きに合わせて補正し、疑似的に両眼視の状態を作り出す方法です。
特に斜視のせいでものが重複して見えたり、眼精疲労を起こしている場合などに有効とされていますが、全ての斜視に効果があるわけではありません。
手術による治療
眼球を動かす外眼筋(内直筋、外直筋、上直筋、下直筋、上斜筋、下斜筋)の位置を症状に応じて移動させることで、各筋肉間における力のバランスを調整し、目を正常な向きに戻します。